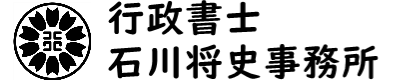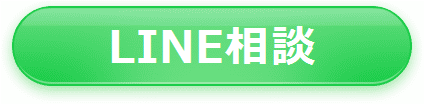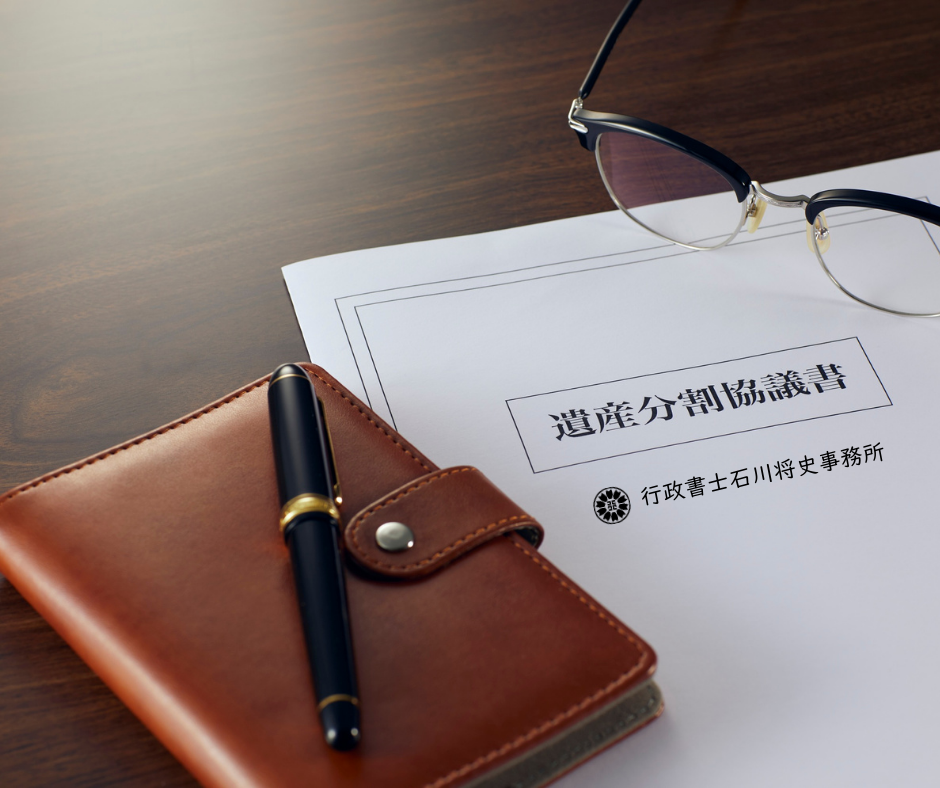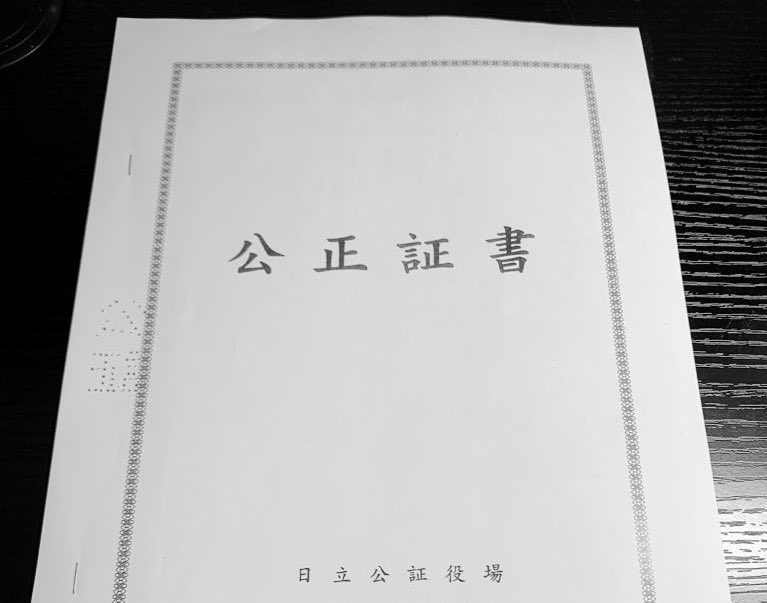法定後見の場合は家庭裁判所への申立てが必要です。申立書の作成は司法書士・弁護士の業務となりますが、当事務所では戸籍収集や財産調査、申立てに関するご相談・アドバイスなどでサポートいたします。
4. よくあるご質問(FAQ)
成年後見制度サポートのご案内
🌸 大切な方の権利と財産を守る、成年後見制度について
成年後見制度は、高齢者や障がいを持つ方々の財産管理や生活支援を行うための制度です。認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の権利や財産を守り、安心して生活を続けることができるようサポートします。
当事務所では、豊富な経験と専門知識をもとに、お客様一人ひとりに最適な後見サポートを提供しています。
💡 こんなお悩みはありませんか?
- 親の認知症が進んで、銀行手続きができなくなった
- 障がいのある子どもの将来が心配
- 一人暮らしの高齢者が悪質商法の被害に遭いそう
- 自分が元気なうちに将来の準備をしておきたい
成年後見制度が解決のお手伝いをします。
1. 成年後見制度の役割
- 財産管理: 銀行の手続きや不動産の管理など、重要な財産を安全に管理します
- 身上監護: 医療・福祉サービスの契約、住居の確保など生活に関する法律行為をサポート
- 法的支援: 法律に基づいた適切な判断をし、本人の権利を守ります
- 悪質商法からの保護: 不当な契約の取消しなど、被害から本人を守ります
2. サービス内容
- 任意後見契約書作成: 将来に備えた任意後見契約の作成をサポートします
- 法定後見申立て支援: 戸籍収集、財産調査、申立てに関するご相談・アドバイス(申立書作成は司法書士・弁護士の業務です)
- 後見人就任: 家庭裁判所から選任された場合、後見人として業務を行います
- 継続的な相談対応: 後見業務に関する各種ご相談にお答えします
3. 成年後見制度の種類
■ 法定後見制度
すでに判断能力が不十分になった方のための制度です。家庭裁判所に申立てを行い、後見人等を選任してもらいます。
- 後見: 判断能力が全くない方(重度の認知症など)
- 保佐: 判断能力が著しく不十分な方(中程度の認知症など)
- 補助: 判断能力が不十分な方(軽度の認知症など)
■ 任意後見制度(当事務所おすすめ)
本人がまだ判断能力があるうちに、自分が信頼する人を後見人として指定する制度です。判断能力が低下した際に、スムーズに後見人がサポートを開始できるようにします。
- 自分で後見人を選べる
- どんなサポートを受けたいか事前に決められる
- 元気なうちに準備できるので安心
家族(配偶者、子、兄弟姉妹など)のほか、行政書士、司法書士、弁護士などの専門職、社会福祉法人などが後見人になることができます。家庭裁判所が本人に最も適した人を選任します。
家庭裁判所への申立て費用は数千円程度です。専門職が後見人になる場合、月額2~6万円程度の報酬が必要になります。資産や業務内容によって異なりますので、詳しくはご相談ください。
任意後見は元気なうちに自分で後見人を選び、契約内容も決められます。法定後見は判断能力が低下してから家庭裁判所が後見人を選任します。自分の意思を反映したい場合は任意後見がおすすめです。
財産管理(預金管理、年金受給、税金納付など)と身上監護(医療契約、介護サービス契約、住居確保など)を行います。ただし、実際の介護や日常の世話は後見人の業務には含まれません。
後見の場合は重要な契約等ができなくなりますが、これは本人を保護するためです。保佐・補助では必要最小限の制限にとどまります。本人の意思をできる限り尊重しながらサポートします。
はい、可能です。家族が後見人になった場合でも、困ったときには専門職にご相談いただけます。また、複雑な手続きが必要な場合は、専門職との複数後見(複数の後見人が選任される制度)という形でサポートを受けることもできます。複数後見では権限を分掌することで、それぞれの得意分野を活かしたサポートが可能になります。
📩 ご相談をご希望の方は、LINE または
メールフォームよりお気軽にご連絡ください。
5. コスモス成年後見サポートセンターの強み
🏛️ 公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター所属
私は、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターに所属しており、以下の安心をご提供できます:
- 不正防止システム: 業務管理を徹底し、透明性の高いサポートを提供
- 損害賠償保険: 万が一に備え、しっかりとした保険に加入
- 専門知識: 成年後見に特化した豊富な知識と経験
- 継続サポート: 長期間にわたる安定したサポート体制
6. サポートが必要なケース
- 認知症の方: 銀行手続きや契約行為ができなくなった場合
- 知的障がいの方: 成人後の財産管理や生活サポートが必要な場合
- 精神障がいの方: 症状により判断能力が不安定な場合
- 高次脳機能障がいの方: 事故や病気により判断能力が低下した場合
- 身寄りのない方: 頼れる家族がいない場合
- 将来への備え: 元気なうちに任意後見契約を結んでおきたい場合
6. ご相談から開始までの流れ
8. ご相談いただいたお客様の声
「母の認知症が進行してきて、成年後見制度について相談しました。制度の仕組みや手続きの流れを詳しく教えていただき、今後の方針を決めることができました。」(50代女性)
「将来が心配で任意後見について相談しました。自分で後見人を選べることや、元気なうちに準備できることがよく分かりました。前向きに検討してみたいと思います。」(70代男性)
「親族だけでは成年後見の手続きが不安でしたが、石川先生に相談して必要な書類や手続きの流れが整理できました。安心して進められそうです。」(40代男性)
9. まとめ
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の権利と財産を守る大切な制度です。早めの相談・準備により、より良いサポートを受けることができます。
ご本人やご家族の安心のため、お気軽にご相談ください。専門知識と豊富な経験で、あなたの大切な方をしっかりとサポートいたします。
💁♂️ 初回相談は無料です。「どこから始めればよいか分からない」という方も大歓迎です。
👇 お好きな方法でご相談ください
※ 争いごとになっている問題、税金に関する問題、登記に関する問題など、行政書士の職務の範囲外の問題については、ご相談に応じることはできませんので、予めご了承ください。